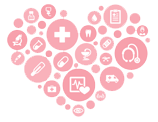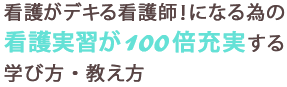アセスメントを書く時に時間がかかる人に共通すること
いつも、ありがとうございます。
ローザン由香里です。

アセスメントを書く時に時間がかかる人に共通すること
それは、
「書く」ということと、
「考える」ということを、
同時に行っている、ということ。
先日、サポート中の学生さんから、「書いてるうちに、何がいいたいのか、わからなくなる」というご相談を受けました。
これ、アセスメントを書くときに、時間がかかるときの主症状です。
「私も、同じ症状がすでに出てる!」
と気がつかれましたか?
気がつかれたのでしたら、ラッキーです。
悩み、というのは、「これ、困るな」と気がつく=自覚する、ことが、解決の一歩だからです。
気がつくことができないと、変えようがありません。
解決までの道のりの、第一歩、おめでとうございます。^^
*
考えながら、書いているという場合、ひょっとすると、
アセスメントをする、ということを、
アセスメントを書く、ということだと、
【勘違い】している可能性が高いです。
アセスメントをする、というのは、対象(受け持ち患者さん)の状態を判断する、ということ。
アセスメントを書く、というのは、対象(受け持ち患者さん)の状態を判断する、
↑これを、頭の中に置いておくのではなく、文字にして表す、ということ。
つまり、順番としては、
1、アセスメントをする
2、アセスメントをした内容を書く
なんですね。
これを、同時に行おうとする、ということは、頭の中で、結論が出ていない状況で、文章を書き出す、ということ。
だから、書きながら、何が言いたいのかわからなくなるんです。
もっというと、【何を言いたいのかを、決めないまま、書き出すので、書きながら、何を言いたいのか、
わからなくなる】のです。
正確には、最初はわかっていたものが、書きながら、わからなくなる、のではなく、最初から、よくわかっていなかった、なんですね。
*
最終的に、アセスメントを文章にしてまとめるとき、
慣れないうちは、
1、アセスメントをする
2、アセスメントした内容を書く
この順序を守ることで、書きながら、わけがわからなくなりながら、書き直しながら、なんども同じことを書きながら、、、
のような、二度手間な繰り返しを防ぐことができます。
書く前に、書きたいことを、確認する。これが、大切です。
アセスメントが書けない、というとき、多くの場合は、
「書けない」ではなく、
「アセスメントができていない」が当てはまることが多いです。
書き方にとらわれず、まずは、文字でも、図でも、箇条書きでも、なんでもいいので、好きなように、書き出してみることから始めるといいです。
▼無料メルマガ<実習がうまくいく学び方>を配信しています。ご登録は無料です。ご不要になりましたら、解除していただけます。ご登録は、>>>こちらから。
▼おさらい看護過程講座;効率よく看護過程を展開する方法を学ぶオンライン講座
▼看護アセスメントマニュアル;アセスメントの手順を学ぶ動画教材
▼完全個別対応LINE(電話)サポート;なりたいあなたになるために、あなたに必要な課題を、あなたに合った方法でご提案します。